
東京ガーデンテラス紀尾井町には、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局のオフィスがあります。このデジタル行財政改革会議事務局で参事官を務める小林剛也さんは、統括総括とスタートアップを担当しています。デジタル行政財政改革会議とはどのような組織なのか、行政ではデジタルを活用してどのような取り組みを行っているのか、人口減少や高齢化がもたらす地方の課題に有効なDXや、日本がリードするDXの可能性、そして東京という町の再考…と、具体的な事例とともに教えていただきました。
デジタル行財政改革会議とは?
ーそもそも、内閣官房「デジタル行財政改革会議」とは、どのようなことを目的に発足された組織なのでしょうか?
急激な人口減少社会への対応として、利用者起点で我が国の行財政の在り方を見直し、デジタルを最大限に活用して公共サービス等の維持・強化と地域経済の活性化を図り、社会変革を実現することを目的に、2023年10月、岸田首相の下にデジタル行財政改革会議が設立されました。担当大臣は、河野太郎大臣です。
ー「デジタル庁」の名称はよく耳にしますが、内閣官房デジタル行財政改革会議とどのような位置関係にあるのですか?
内閣官房デジタル行財政改革会議は、いわばデジタル庁等のホールディングスカンパニーのようなイメージを持っていただければと思います。内閣官房デジタル行財政改革会議は、デジタル庁のほか、規制改革推進会議、行政改革推進会議、デジタル田園都市国家構想実現会議という4つの会議を束ねて、司令塔のような役割を果たしているんですよ。
ー内閣官房デジタル行財政改革会議でどのようなことに取り組まれているのか教えてください。
教育、交通、介護、子育て・児童福祉、防災という各分野と、それらを横断的に繋ぐ役割であるスタートアップという、6つの分野を設定し、また、最近では医療分野にも力を入れ始めているところです。特に住民生活に密着して、デジタルを使うと生産性が上がりやすい分野を特定しながら改革を進めているところです。
ーデジタル化によって、どのような課題を解決することが期待されているのでしょうか?
これまで「行政改革」というと、どうしても供給者側の目線で議論をすることが多かったのですが、内閣官房デジタル行財政改革会議では、「利用者起点」といってユーザーの視点から行財政サービスの在り方を議論することが鍵となっています。既に多くの企業では当たり前になっている取り組みではあるのですが、そのように、利用者の目線で行財政サービスがどのように映っているのかを考えるということが大きな特徴といえるでしょう。より具体的にいえば、例えば、2019年に閣議決定された「GIGAスクール構想」と呼ばれるプロジェクトがあります。新型コロナ感染拡大の影響でこの計画は前倒しになったのですが、デジタル行財政改革では、全国の小中学校の教育現場で端末を1人1台に配布し、通信ネットワークを整備することで、「生徒一人ひとり」という「利用者」が、公正に学ぶ機会を持続的に得られることや、教職員の仕事の効率化などが期待されています。
ーデジタル教材を利用することで、日本中どこにいても学ぶことができるようになるということですね。
例を挙げると、「みんなで筋肉体操」というNHKが配信しているわかりやすい動画があります。その配信があることを知っていれば、体操に詳しい先生がいない学校でも同じように取り組むことができるでしょう。どこにいても良質で効果的な教育を受ける機会が得られるということですね。そして、そのようなギガ端末が、教育現場で適切に使われているか、使う先生のスキルはどうか、より最適なシステムや便利なアプリとは…といったことを、令和5年10月に開かれた第1回目の会議で教育関係の専門家と、総理と関係大臣を交えてディスカッションしました。その内容を踏まえて、官邸で総理と関係大臣と有識者による会議を行い最終決定するのですが、その手前における、利用者起点で課題を発掘し対話を重ねる「課題発掘対話」が重視されていることが重要です。今年4月には、第8回目の対話が開かれたところですよ。
ーいわば、一般市民の代表者から課題を吸収し、課題に取り組んでいく場を設けているということですね。
例えば、学校の先生や保護者の代表から直接的に課題を聞くことによって、構造的に課題を把握していきます。「先生は残業が多いですよね」とか、「ギガ端末が有効に使われていない」という声に対して、では先生の側から見たらどうなのか?といったことや、出欠確認や通信簿の記入など膨大な紙ベースの仕事に追われてしまいがちだが、本当はもっと生徒に向き合いたいと思っていること、デジタル教材を有効に使いたいと思っているけれども、実は他の業務改革に課題があってできない…といった、現場の実情を聞きながらではどうするべきなのか?と解決していくということですね。デジタルに任せられるものはどんどんデジタル化して先生の負担を減らし、本来もっと力を入れたいと考えている、生徒に向き合ったり、保護者の話を聞いたり、そういった時間を設けられるようにしたいと考えています。
ー構造的に問題を把握することが大事なのですね。
ええ。教職員の残業の問題は「終業時間だからルールに従って帰宅してください」ということを定めるだけでは、当然解決しませんよね。一つの問題があらゆる問題に繋がっているわけですから、全体的かつ構造的に、横断して問題を把握することが利用者起点という意味では大事だと考えています。
行財政とスタートアップの協働
ー様々な改革を推進していくなかで、必要となる民間力とは?
民間企業と組むことも一つの特徴として挙げられます。DXは、多くの中小規模自治体では苦手な分野であることが課題となっている現状において、スタートアップが保有する斬新なアイデアと技術、そして機動力によって、業務改善を促す大きな期待があります。そこで、スタートアップをはじめとする企業と組んでいくことが、ソリューションとして非常に有力な手段だと考えています。ですから、実際に、課題発掘対話や本体会議といった会議の他にも、デジタル行財政改革に携わる事務局の我々職員は、日常的にオンラインミーティングでスタートアップ業の方々の話を聞いています。また、NPOの方々にヒアリングすることも多いですね。というのも、自治体、利用者、そしてベンチャーの視点というのはそれぞれ異なることが多いので、それらを円滑に繋ぐ役割を担う中間支援団体が発達してきています。その中間支援団体の方々から話を聞くことによって、多角的に改革を進めることができるようになるのですね。
ー実際に取り組みが進められている具体的な事例はありますか?
スタートアップ育成については、内閣官房の「スタートアップ育成5か年計画」や経済産業省がかなり進めているところですので、デジタル行財政改革の役割としては、行政側のニーズを中心にして課題を捉え、これまで人力でやっていた分野をスタートアップと組むことによってデジタルや最新技術で解決することを目指しています。具体例を上げましょう。私が兼務しているデジタル田園都市国家構想会議では、デジタルを活用して地域の課題解決に取り組む優良事例を表彰する「Digi田(デジでん)甲子園」という取り組みを進めています。2023年には、愛知県豊田市がスタートアップと協働し、上下水道の水道管の維持管理をAIと人工衛星を使い、漏水調査の距離を従来の10分の1、調査期間を60か月から7か月に短縮することに成功した事例が内閣総理大臣賞を受賞しました。
ー今後、そのような取り組みが海外へ向けて発信される可能性も?
日本は課題先進国と謳っている国でもありますから、国内で実装したビジネスを持って日本発のスタートアップが世界の市場に進出するケースもあるでしょうし、逆に、海外のスタートアップが日本の公共領域のデジタル化などを目指して日本に来ることも考えられます。いずれにしても、社会課題が日本の新たなチャンスとなり得ることには注目が集まっています。そのように海外へ発信・展開していけば、「北欧モデル」みたいな形で「日本型社会経済モデル」として日本国や日本企業のブランディングにもなるでしょう。
地方の取り組みから学ぶこと
ー首都圏と地方での取り組みの違いはありますか?
実は一概に言えないのですが、一般的には、様々な施策というものは東京が進んでいると思われていますよね? でも、地方には東京にいると気づかない社会課題もたくさんあったりするものなのです。例えば私が2020年から2023年まで勤めていた山形県庁では、民間のIT企業と組み、除雪の取り組みを行いました。ひとえに除雪といっても、どの道路にどれだけ降雪量があるのか全てチェックしなければなりません。これが相当のコストがかかる作業で、地方に行けば行くほど人口密度が低く、職員の数も限定されるなか大きな苦労を要するんですね。そこで、市長や職員が利用する公用車の前後にカメラを装着し、自動的にデータを転送して、走行した場所の積雪状況を把握できるようにしました。これにより、除雪にかかる経費や市民からのクレームが減ったというデータも得られています。
また、東京都庁では「GovTech(ガブテック)東京」という、DXを推進する行政改革が進んでいるので、デジタル行財政改革会議の事務局でも都と連携して取り組みを行っています。政府としては、こうした東京都の取組みと、前述したような地域の事例とを有機的に組み合わせて新たなソリューションを見つけていくことが大事だと思っています。都市部であれ地方であれ、私たちのような公的セクターの職員も、しっかり現場に入って実態を把握することが重要ですね。
ー行政とベンチャーがタッグを組む取り組みはアメリカをはじめ海外が先進している面もあると思いますが、日本独自の発展の仕方はありますか?
技術をどのように応用するのかという応用の段階では、日本独自の分野が台頭してきていると思います。日本では例えば、少子高齢化による介護問題が大きな課題になっていますが、高齢者が転倒した際の骨折対策として、浜松発のベンチャー企業、マジック・シールズが手がける特殊なクッション材の技術を使った床材が、実際に介護施設などで導入され始めています。この企業は、VC(ベンチャーキャピタル)などを引受先に1億4000万円を調達したことが話題になりましたが、そのように日本独自の課題から新たなビジネスが創出されているんですよ。
ー日本から発信できる技術には、まだ可能性が広がっているのですね。
ええ、人口減少・高齢化という社会的背景とした「実需」が日本にはあり、日々、官民挙げて解決に取り組んでいますので、可能性があります。また、日本はものづくりが強いですからね。ITそのものはやはりGAFAMが強いですけれど、ものと結びつけてどのように社会へ適応するかということは、ものづくりが基礎にあると強いと思います。さらに、デジタル行財政の文脈においても、人口減少における社会生活の維持というテーマに関しては、日本が現在トップランナーだと言えるでしょう。
例えばある山奥の村で、高齢者の方々に防災無線の代替としてタブレット端末を配布して、災害時などに逃げ遅れないよう周知する取り組みも行われています。初めはこのように防災無線の役割で配布したのですが、だんだん防災にまつわる情報をもとにしたイベントを開催したり、健康維持のための方法を共有したりと、地域の様々なお知らせをすることによって、高齢者の方々も自然にタブレットが使いこなせるようになってきているんですよ。
このように、デジタル技術が発達するなかで、どのようにインクルーシブ(包摂的)な社会をつくるのか?という課題に対する一つのソリューションが、日本の各地の実践にあるのではないかと考えています。政府の役割としては、こうした事例を現場に入って分析し、全国的に共有したり、様々な導入支援を行ったり、といったことが重要になってきますね。
ーとは言っても、やはり高齢者のなかにはデジタルへの抵抗感を強く持っている方も多いのではないかと思うのですが、デジタル化を浸透させるために必要だと考えていることはありますか?
デジタル・ディバイド(情報格差)という言葉があるように課題はあります。しかし、地道に取り組んでいくことが重要であり、one fits allの解決策というものは存在しないと思っています。現在、デジタル庁とデジタル行財政改革が共同で取り組む「デジタルマーケットプレイス(DMP)」が始まったところです。日本国内には1800もの自治体があるのですが、各自治体が地域のお買い物券なんかを配っていたりしますよね。しかし、そのチケットを印刷するコストが値引き額よりも高いというほど相当の負担になっていたわけで、そのようなサービスをアプリで利用できることがスムーズだということは一目瞭然ですよね。ご高齢者でスマホを持っている方も多いですから。一方で、これまでは自治体がアプリを導入していても、使用するアプリがバラバラでアプリの開発費用も軽視できないものでした。この問題を改善するために導入しようとしているのがDMPという仕組みです。政府が提供するプラットフォーム上で、一定の技術要件を経たアプリが登録できて、信頼の置けるアプリとして自治体が導入できます。SaaS(Software as a Service=アプリをインターネット経由で提供するシームレスなクラウドサービス)ですから、ユーザーは難しい設定の必要がなく、すぐに利用できる状態となります。4月にα版がリリースされ、今年度の後半には実際に自治体で試用が開始される予定です。
ーそのような一連の改革は、コロナ禍の後押しもあったのでしょうか。
コロナ禍では企業をはじめ役所でもリモートワークが推進し、社会環境の大きな変化がありました。とくに日本人には「直接会わないと失礼だ」といった気質があったと思いますが、気づけば今は「相手の時間を取るほうが失礼だ」といった意識へ変化したのではないでしょうか。私は、この社会変化を、ある一定のスレッシュホールド(閾値)を超えた状態、と見ています。日本はなかなか変化が起きにくい社会だと言われますが、リモートワークは、コロナ禍で止むを得ず起きた変化が、常識として定着した好例ですね。
ーリモートワークをステータスとして人材を募る企業やスタートアップも増えたと感じます。
ええ、とくに人材戦略においては重要ですよね。オフィスを都内や市内などに構えるのは賃料も高くなるので、基本的にリモートでやってくださいというスタートアップが増え、実際にそのほうが効率も良いということもありますよね。逆に、対面でのミーティングは、特別な意味があったり、より深い議論をしたりする場面で選択する。そのように柔軟に使い分けながら、ハイブリッドな働き方ができることがより求められるよう社会になるのではないでしょうか。
アナログの存在は意味が変化していく
ー小林さんは、陶芸や絵画をはじめ芸術に関わる活動もされていますよね。山形県庁に勤めていた際には地元の陶芸家の方々と共に展覧会を開催するなど、デジタルではできない、手を使ったものづくりや地域の人々との実空間での交流を大切にされていることが窺えます。
デジタル化というのは、実は30年前ほど前からからずっと言われ続けてきたことで、デジタルの発想はそもそもあったんですよね。回線速度が遅いとか、モバイル化されていないといった時代を経て、現在は即時に使えるようになりました。従来は例えば、首都圏と地方の企業が取引する際に直接出向かなければならなかったことが、時間やコストなど多くの制約を生んでいましたが、現在はオンラインで解決することができます。こうなると、日本国内だけでなく、中国もアメリカもアフリカもヨーロッパもみんな同じ競争条件になるわけですよね。そのようにフラット化する社会のなかで、何が大事なのか、どのように付加価値を上げていくのかということを考えると、反対に、土着というか、アナログの部分がすごく重要になってくると思えてなりません。ものづくりや芸術には、デジタルだけでは担えない部分が大きいと思います。そういった意味でも、デジタルと対比してのアナログは、将来消えていくのではなく、その意味や定義が変化していく、ということなのではないかと考えています。
東京という町を考え直す必要性
ー2024年4月に「KIOI TALK」が本格的にスタートし、小林さんにもご登壇いただいています。KIOI TALKでは、様々な分野の有識者の方々とのディスカッションを通じて、東京・紀尾井町から日本の魅力を様々なかたちで発信していく予定ですが、東京という町から発信する意義や、イベントに期待することなどメッセージをお願いします。
私自身、デジタル行政改革会議事務局が東京ガーデンテラス紀尾井町の上階に入居したことをきっかけに、紀尾井町という町が江戸時代の歴史に縁のある土地だということを改めて認識することになりました。そもそも江戸・東京は徳川家康公の熟考をもとに設計された都市で、風水や、上水道の整備など、様々な知恵や技術が結集しています。しかし、もう400年も経っているんですから、家康公にいつまでも甘え続けていてはいけないと思います。江戸の街づくりをリスペクトしつつ、東京という場所がより魅力的であるために、現代の人々が自分たちで東京について考えないとならない。もう一度、東京を見直す時代に差し掛かっているんじゃないかと思っているんです。
コロナ以後の現実を見てみると、1都3県には年間10万人以上の人々が流入しています。地方創生を今後ももっともっと力を入れて続けていくと同時に、地方創生の成果が着実に実を結ぶためにも、東京という都市の在り方を日本人全員で、きちんと考えていく必要があると思います。
KIOI TALKでは、紀尾井町という地域に密着しながら、様々な分野の専門家と対話を重ねて意見交換をして、フィールドワークも大切にしながら、これまで行われてきた多様な活動を可視化し、今後の取り組みを考えていただきたいです。それは、今日からすぐに活かせる便利なテクニックというものではなく、長い目で見た時に何かに役に立ってくるような視点が得られる場、単なるビジネスセミナーでもカルチャーセミナーでもない言論空間になったらと期待しています。いま、DX、グローバル化、地方創生、ESG等々、様々なキーワードが世の中で渦巻いていますね。それらについて、一歩引いた場所から自分の頭で思考できるような、知的リトリートの場が生まれるのが理想だと思います。
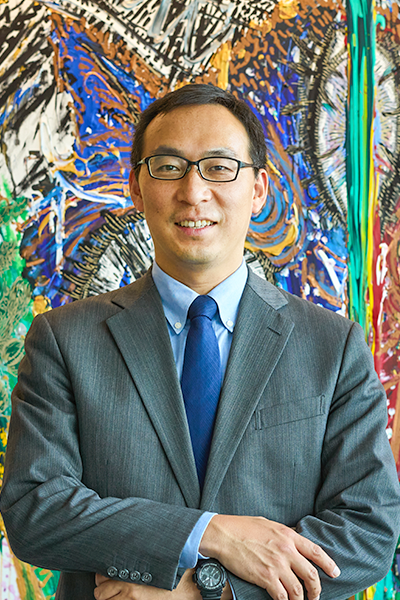
小林 剛也(こばやし・ごうや)/内閣官房デジタル行財政改革会議事務局参事官
2003年、財務省入省。財務省の各部署のほか、欧州復興開発銀行(ロンドン)、内閣府東日本大震災被災者生活支援チーム、在ドイツ日本国大使館などでの勤務経験を持つ。山形県庁でみらい企画創造部長、総務部長を歴任し現職。内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局参事官も務める。



