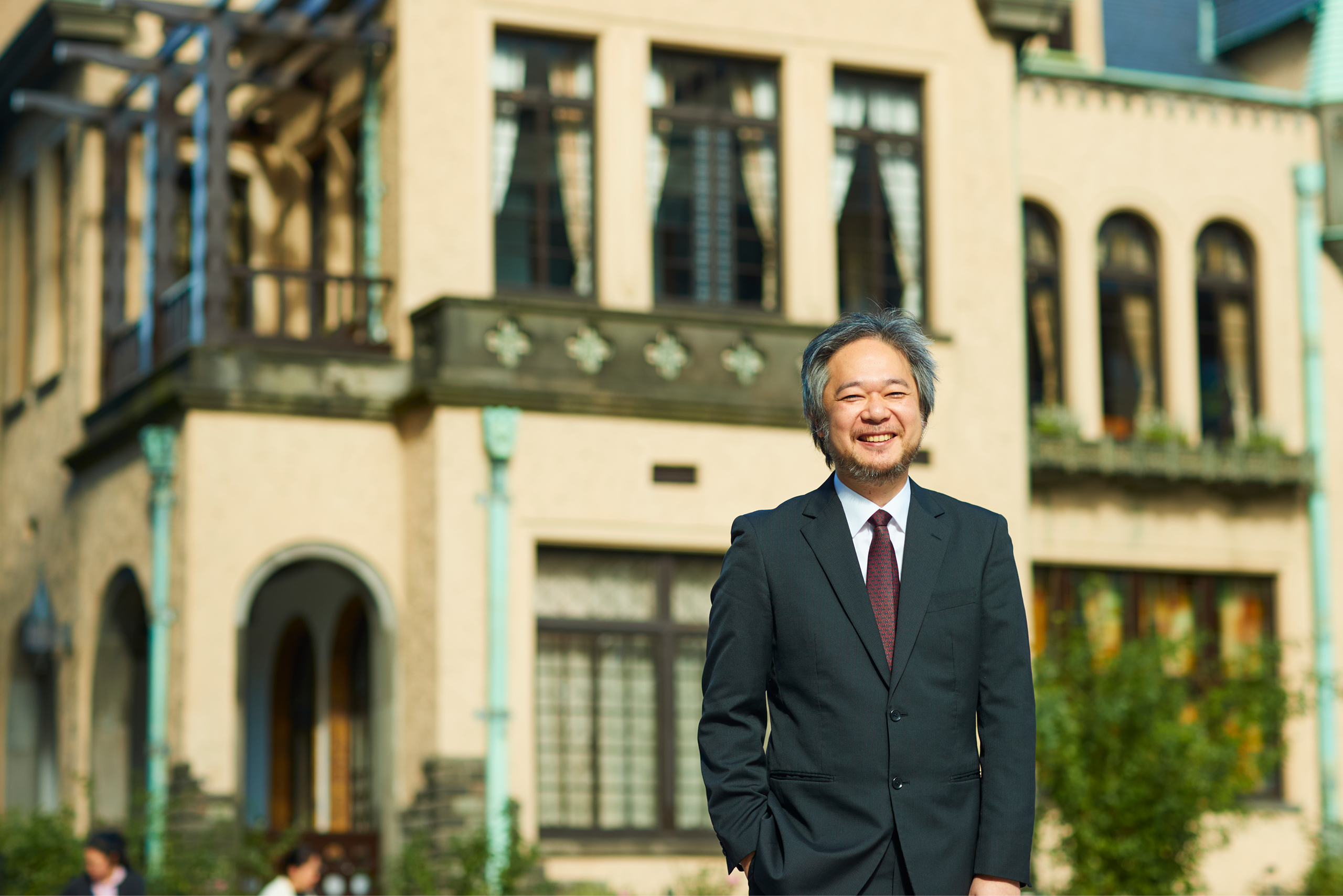
東京ガーデンテラス紀尾井町では、東京藝術大学の協力を得て、ミニ演奏会「KIOI CONCERT」や新年の恒例行事「ニューイヤー・コンサート」など、クラシック音楽の演奏会を定期的に開催しています。ビギナーでも気軽に楽しめる機会として多くの人にご好評をいただいているこれらのコンサートで、楽曲の編曲を手がけているのが音楽家の佐野秀典さんです。年間100曲以上をアレンジしているという佐野さんに、編曲という仕事や、来たる「ニューイヤー・コンサート」のこと、そして音楽が持つ可能性について話を伺いました。
原曲の世界観はそのままに、
楽器編成を変えたり、長さを変えたり。
編曲の仕事は奥が深い。
「作曲や編曲をしたり、音楽祭や音楽関連のイベントの企画や制作をしたり。東京都交響楽団では、楽譜の管理を担うライブラリアンとして仕事をしています。自分としても掴みどころがないなと思うのですが(笑)、クラシック音楽を中心とした、音楽の“なんでも屋”だと捉えてもらえたらいいかもしれませんね」。自身の仕事についてそう話す佐野秀典さん。作曲家、編曲家、音楽コーディネーター、オーケストラ・ライブラリアンなどさまざまな肩書きを持ち、幅広い現場で活躍しています。
彼の多岐にわたる仕事の中で、多くの比重を占める一つが編曲。東京ガーデンテラス紀尾井町で開催される「KIOI CONCERT」や「ニューイヤー・コンサート」でもさまざまな楽曲の編曲を担当しています。そもそも編曲とは、どのような仕事なのでしょうか。
「クラシックの楽曲には既存の楽譜がありますが、コンサートの形態によって、原曲とは異なる編成で演奏することが多々あります。一般的なオーケストラが80人程度の編成であるのに対して、例えば『ニューイヤー・コンサート』を演奏する室内オーケストラは20人程度の小規模な編成。オーケストラ編成を見越して書かれた楽曲を演奏する場合、少ない編成に合わせてアレンジしなければなりません。とこんなふうに、その時々の編成に合わせて、原曲のイメージを損なわないままに楽譜を再構成するのが“編曲”という作業です」
時には、プログラムに合わせて楽曲の長さをコンパクトにしたり、客層に応じて聞きどころを凝縮した構成に変更したり、あるいは奏者の特性に合わせてアレンジすることもあるのだとか。どんな空間、どんな編成で演奏されるのか、そしてどんなお客さんに届ける音楽であるか、さまざまな角度から考えることが求められる奥の深い仕事です。
そんな佐野さんの元には、編曲にまつわるさまざまなオーダーが舞い込んできます。その一つが、2024年5月に開催された仙台フィルの定期公演。人気アニメシリーズ『コードギアス』の音楽をオーケストラで演奏するために、楽曲を編曲してほしいという依頼でした。
「プロのオーケストラが定期演奏会でアニメ音楽を演奏するという画期的な企画で、2時間の公演で演奏される全曲の編曲を任せてもらいました。ファンの多い作品だから楽曲の世界観を崩してはいけないし、とはいえ、あくまで定期公演なのでオーケストラ自体の魅力も感じてもらいたい。ソロを取り入れたり、パートに変化をつけたりしながら、試行錯誤しました。また、普段はアニメのBGMとして流れている楽曲群なので、フレーズの重複が多くて単調になりがちなんですよね。いかに魅力的にするかにも苦心しました」
一方で、東京ガーデンテラス紀尾井町での仕事で印象に残っているのは、2022年の「ニューイヤー・コンサート」。コロナ禍真っ只中ゆえ、合唱は盛り込まず、ピアノと弦楽器だけの編成でベートーベンの第九を演奏することとなりました。
「日本では年末の風物詩として馴染みがある第九ですが、コロナ禍では飛沫の問題があり、合唱を伴うことから各地のコンサートで避けられる傾向にありました。ならば年始のこの機会に自分たちが第九をやろうと。編曲のみならず、感染対策をしながらコンサートを催すことがかなり大変でしたが、コンパクトな形であれ実現できたことには、すごくやりがいを感じましたね」

ピアノと出会った幼少期。
そして夢中になったバンド活動を経て、
本格的な音楽の道へ。
そもそも佐野さんと音楽との出会いは、幼稚園の頃にまで遡ります。彼が通っていたのは、週に1度、ピアノのレッスンがあるというユニークなカリキュラムを持つ園。そこで習い始めたのが最初でした。「当時はもう嫌で嫌でたまらなかった(笑)。全然練習もしていかなかったし、サボってばかりだったと思います」と当時を振り返ります。
しかし「せっかく始めたのだから」というご両親の勧めもあり、小学校に入って以降もなんとなくピアノを習い続けていたという佐野さん。そして、高校生になるとバンド活動に夢中に。そこで初めて、音楽を本格的に学びたいという思いが芽生えてきたと言います。
「R&Bやジャズが好きになって、オーティス・レディングや、ハビー・ハンコックなんかをよく聞いていましたね。バンドでもカバーからオリジナルまでいろんな楽曲を演奏しました。すごく楽しかったし、ピアノはずっとやっていたので、何も考えなくても手ぐせで弾けてしまう。でもそれは言い換えれば、できる範囲のことしかやらないということでもあるんです。一度きちんと勉強しないと、技術的にもこれ以上広がっていかないなと痛感しました」
高校卒業寸前のタイミングで音楽の道に照準を合わせ、東京藝術大学に進学。入学してからは、どっぷりクラシック音楽漬けの毎日を送ることになりました。
「クラシック音楽の知識を学んだ後に、R&Bやジャズにまた戻ることも考えなかったわけではないんですが、作曲や編曲の仕事を始めたこともあり、そのまま今の道に進むことになりました。今も大学時代の延長のまま仕事をしている感覚がありますね」
幅広い人が行き交う紀尾井町だからこそ、
クラシック音楽の魅力が凝縮された
編曲やプログラム構成に。
そんな佐野さんが、編曲を手がけると共に、当日舞台上に立って自ら楽曲の魅力を解説してくれる年1度の機会が、「ニューイヤー・コンサート」です。東京藝術大学の卒業生たちによる特別編成の室内オーケストラが演奏するコンサートで、2018年のスタート以来、東京ガーデンテラス紀尾井町の新年の恒例行事となっています。
「新年のイベントなので、明るく、楽しく、というのが一番大切にしていること。東京ガーデンテラス紀尾井町には、近隣にお住まいの方もいれば、働いている方もいるし、遠くから足を運んでくれる方もいる。いろんな人が行き交う場だからこそ、クラシック音楽に特別詳しくなくても楽しめるようなプログラム構成や編曲を意識しています。その年のテーマや曲目については、運営に関わるスタッフの方々と活発にアイデアを出し合いながら決めていますね」
もともとは、80年以上の歴史を持つ元日の恒例行事、ウィーン・フィルの「ニューイヤー・コンサート」に着想を得て始まったこのコンサート。開催1回目となった2018年のコンサートでは、ウィーン・フィルのコンサートを踏襲し、《美しく青きドナウ》や《ラデツキー行進曲》など、ヨハン・シュトラウス祭りとも言える楽曲が揃いました。以来、回を経るごとに、バレエやオペラを取り入れたり、お客さんが手拍子をしながら楽しめるメドレーをやってみたりなど、さまざまな工夫が施されています。そして、今年の「ニューイヤーコンサート」は、数年ぶりに室内オーケストラ1本での構成。ヨハン・シュトラウスの楽曲のほか、管弦楽の名曲《新世界》や、メルヘン・オペラで人気の《ヘンゼルとグレーテル》が演奏される予定です。
「《新世界》は、オーケストラの名曲を、あまりクラシック音楽に馴染みがない方にも感じてもらいたいとの思いで、スタッフの方からアイデアをいただきました。聞き所を凝縮したコンパクトな構成でお届けする予定です。一方で、《ヘンゼルとグレーテル》は、世界的にも有名な子供向けのオペラ。童謡としても馴染みがあると思いますし、作曲家フンパーディングによる楽曲もすごくいい。小学生から中学生くらいの子供たちにも気軽に楽しんでもらえたら嬉しいですね」

コンサートの醍醐味は、
空間を共にし、
同じ音を分かち合うことにある。
紀尾井町においても、「ニューイヤー・コンサート」や「KIOI CONCERT」が街と人、あるいは人と人とを繋ぐ一つの機会になっているように、近年では、地域の中でつながりを生んだり、地域を盛り上げたりする起点としての音楽の可能性が広がりつつあります。例えば、佐野さんが携わっている、岐阜県の可児市文化創造センターの取り組みもその一つです。
「可児市文化創造センターは、劇場やワークショップルーム、ギャラリーや練習室などを持つ文化普及支援施設で、芸術の殿堂ではなく“人間の家”にしようというコンセプトを掲げています。例えば年に一度、音楽家数名が数日滞在し、子供たちと一緒に音楽を作ったり、コンサートのリハーサルの様子を地域の方たちに公開したりしてます。時には音楽家が小学校に赴いて教室で出張授業をすることもあります。顔が見える関係性ができることで、市民の方にとっては音楽家をより身近な存在に感じることができるし、音楽家としても新しいファンができる。双方にとって貴重な機会になっていると思いますね」
ひとたび関係性ができると、子供たちは放課後に気軽に劇場に遊びに来るように。大人たちも自然と集まってきて、相互にコミュニケーションが育まれるのだといいます。人と人との関係性が希薄になりがちな昨今、「繋がるためには、同じ空間にいることが大事だと思うんです」と佐野さん。最後に、こう続けてくれました。
「かつてクラシックのコンサートが社交場だったように、音楽には人と人とを繋ぐ不思議な力があると思うんですよね。『ニューイヤー・コンサート』を例にしてみても、新年らしいすがすがしい気持ちで訪れる方もいれば、辛い気持ちを抱えている方、いろんな思いを持った方が来ると思うんです。コンサートなので、話すことで共有できるわけではないけれど、同じ空間で、同じ生の音楽を聴き、想いを共有することで、気持ちを分かち合える部分もあると思うんですよね。ぜひ一度、空間を共にして音楽を聴く楽しさを味わってほしいなと思いますね」


佐野 秀典(さの・ひでのり)/音楽家
秋田県大曲市生まれ。東京藝術大学音楽学部作曲科卒業、同大学院修士課程修了。牧野由多可賞作曲コンクール大賞等を受賞。ウィーン・リング・アンサンブルや、新日本フィル、大阪フィルなどで多くの編曲を手がけるほか、各地の音楽祭の企画制作運営や、可児市文化創造センター音楽コーディネーターを、東京都交響楽団ではアシスタント・ライブラリアンを務めるなど、幅広く活躍している。



